投資の始まり:迷走と損失
私が株式投資を始めたのは2019年8月。最初は株主優待や短期売買を繰り返し、何とか利益を出そうと必死でした。しかし手法もルールも固まらず、場当たり的な取引を続けた結果、含み損は−20万円まで膨らみました。あの頃は「自分には投資のセンスがないのでは」と悩んでいました。
東証の要請と高配当株へのシフト
転機となったのは2023年3月、東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願い」を公表したことです。PBR1倍割れ企業への改善要請をきっかけに、自社株買いや増配を発表する企業が増え、株主還元が強化されました。
私はここで高配当株投資にシフトしました。業績が安定していて割安に放置されている銘柄を集めた結果、一時は−20万円だった資産は2025年9月には+289,261円の含み益に。さらに配当金229,625円も積み上げ、投資の基盤を固めることができました。
S&P500との比較で突きつけられた現実
順調に見えた高配当株投資ですが、S&P500と比較すると衝撃の事実がありました。もし同じ期間、全額をS&P500に投資していたら、100万円近く利益が多かったのです。毎日のように投資に時間を割いてきた私が、何もせずインデックスを持っていた投資家に負けていた。この現実は、まさに頭を金づちで殴られた気分でした。
それでも私はFIREの夢を諦めきれませんでした。完全FIREは難しくても「サイドFIRE」なら実現できる。そう考え、私は新しい挑戦を始めることにしました。
短期トレードへの再挑戦
2025年8月から再び短期トレードに挑戦しました。これまでの経験をもとにチャートを見直し、銘柄ごとの需給を意識した結果、月間+20万円以上、勝率8割という成果を残すことができました。
ただし、この短期トレードにおいて最大の壁は「目標株価をどう設定するか」でした。どこで利確すべきか、どこまで伸ばせるのか。これが分からないために過去は失敗していたのです。
ちょる子氏との出会い
そんなとき、彗星のごとく現れたのがちょる子氏でした。彼女のスタイルは、これまで私が学んできた井村俊哉氏、テスタ氏、DAIBOUCHOU氏、DUKE。氏、kenmo氏、株1000氏、エナフン氏といった投資家の手法とはまた違った角度を持っていました。
- ボリンジャーバンドから目標株価を算出
- ニュースや地合いを組み合わせて方向性を読む
- 取引対象は大型株中心というシンプルさ
この斬新なスイング手法に強い衝撃を受け、私は貪るように彼女の考え方を勉強しました。
著名投資家たちの共通点
需給といえばテスタ氏を思い浮かべますが、彼も目標株価についてこう語っています。
「目標株価までは保有する。違ったら損切するだけ。途中の値動きは気にしない」
ここから私は二つの気づきを得ました。
- テスタ氏も値動きだけで判断しているのではなく、しっかりと目標株価を算定している。
- 目標株価に到達するまでの細かい値動きは意識していない。
さらに片山晃氏も「自分のストーリーが間違っていなければ、自分都合で降りることはしない」と発言しています。つまり目先の値動きに惑わされず、方向性が正しいと信じるなら保有を続ける姿勢です。
そしてちょる子氏も「チャートの方向性が違えば損切する」と述べています。視点はやや異なっても、やはり明確な目標を持って行動している点は共通しています。
私の目標株価の算出方法
こうした学びを取り入れ、私は自分なりに目標株価の算出方法を確立しつつあります。
- PER×EPSから理論株価を算出
- その上でボックス理論を組み合わせ、レンジの上限やブレイク後の目安を意識
- 実際の取引では、目標株価付近で出来高や足形、移動平均線を確認し、利確や損切を判断
つまり「理論」と「チャート」を両輪として活用することで、納得感を持ってトレードできるようになりました。
まとめ
2019年に投資を始めて−20万円の挫折を経験し、2023年以降は高配当株で復活。しかしS&P500との比較で現実を突きつけられ、2025年から短期トレードに再挑戦。その過程で「目標株価」という最大の課題に直面しましたが、ちょる子氏や著名投資家たちの考え方から学びを得て、自分なりの算出方法を取り入れることで手応えをつかみ始めています。
これからも割安株で守りを固め、短期トレードで攻める二刀流を磨き、サイドFIREという目標に向かって進んでいきたいと思います。
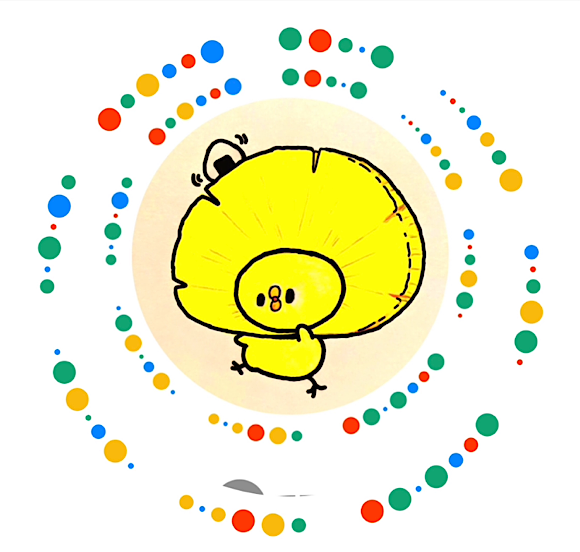

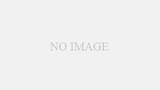
コメント