投資の始まりとファンダ重視の理由
私が株式投資を始めたとき、最初に手を伸ばしたのはファンダメンタル分析でした。理由はシンプルで、チャートはさっぱり分からず、取っ付きにくかったからです。当時はグロース株優位の相場環境で値動きも激しかったため、「業績や財務を積み重ねて分析したほうが安全だろう」と考えたのです。
さらに、当時よく見ていた「ZEPPY投資ちゃんねる」で井村俊哉さんがファンダを丁寧に解説しており、勉強すればするほど成果に結びつく“積み上げ型の努力”のように思えました。しかし、実際にやってみると違和感がありました。学校の勉強のように正解があるわけではなく、どれだけ調べても答えにたどり着けない。積み上げても積み上げても、正しい方向性を外せば成果は出ない。私はいつしか「ファンダは天才肌でないと難しいのではないか」と感じるようになりました。
テクニカルへの視点転換
そんなとき、ZEPPYにテスタ氏が出演しました。内容の細部は忘れてしまいましたが、強烈に残った印象は「チャートのほうが楽そうだ」という感覚でした。
なぜなら、ファンダは積み上げても正しいかどうかが不透明ですが、チャートは「すべての情報が織り込まれた結果が目の前にある」という考え方に基づいています。つまり、チャートを読む力さえあれば、短時間で効率よく利益を得られるのではないか、と考えるようになったのです。
事実、井村氏が「テスタさんと同じ銘柄を仕込んでいたことが何度もある」と語った対談を見たときも、根拠は全く違っていました。井村氏はファンダ的な裏付けを説明しましたが、テスタ氏は「チャートが良かったから」とだけ語り、ファンダはほとんど触れなかったのです。私はここで「ファンダに膨大な時間をかけなくても、チャートが読めれば強い銘柄に乗れる」と確信しました。
ファンダとテクニカルの間で揺れ動く日々
とはいえ簡単ではありませんでした。新高値ブレイク投資法を学び、株探や書籍、YouTubeを貪るように見ましたが、勝率は1〜2割程度。そこで決算期の上方修正銘柄に絞って新高値ブレイクを狙うなど工夫を加え、勝率を3割に引き上げました。
この頃は「やっぱりファンダ?」「いや、テクニカルこそ効率的」と往復を何十回も繰り返す状態。それでも最終的に、テクニカルに軸足を置くのが自然だという結論に落ち着きました。
パワプロに見る自分の感性
なぜ私がテクニカルに惹かれるのか。それを思い出させてくれたのが、かつて夢中になった野球ゲーム「パワプロ」でした。
友人たちは「サクセス」で選手をコツコツ育成していました。これはまさにファンダ型=積み上げ型のアプローチです。一方の私は、対戦で技術を磨いたり、ペナントでGM的に采配を楽しむほうに熱中していました。弱いチームを補強し、選手を入れ替えて勝利に導く。この遊び方は、まさにテクニカル型=状況を読み、今の優位性を判断することに通じていました。
さらに私は、スポーツ新聞の見出しとパワプロに収録された選手データを組み合わせ、実際の選手の能力を推測して会話していました。プロ野球を見ていなくても、「首位打者だからミート力は高いはず」「去年より打率が伸びているから成長したんだろう」と推測し、的確に当てていました。これこそ、チャートから未来を読む感覚そのものだったのです。
学びの積み重ねと取捨選択
こうした背景もあり、私は「やはり自分にはテクニカルが合っている」と感じました。とはいえ完全に独学では限界もあり、月1万円の株サークルに参加したこともあります。そこでは講師が3人いて、ひたすらチャートの見方を解説してくれました。今振り返ると、すべてが正しかったわけではありませんが、役に立つ部分だけは自然と身につき、基礎として今も生きています。
加えて、テスタ氏のYouTube切り抜きや、DUKE。氏の本や過去動画も非常に参考になりました。特に「原点回帰」として見直すと、自分の中にある考えの軸が補強されるような感覚があります。
まとめ
投資を始めた頃はファンダ一辺倒で勉強を積み重ねれば勝てると思っていました。しかし時間をかけても成果に直結しない経験を経て、チャート分析の合理性に気づきました。そしてパワプロでの遊び方を思い返したとき、私はもともと「積み上げ型」ではなく「状況判断型」の感性を持っていたことに気づいたのです。
今では、ファンダは補助的に使いつつ、テクニカルをメインに据えた投資スタイルが私にとって自然な形となりました。積み上げよりも「いまの優位性」を読むことで、自分の性格にも合った戦い方ができているのです。
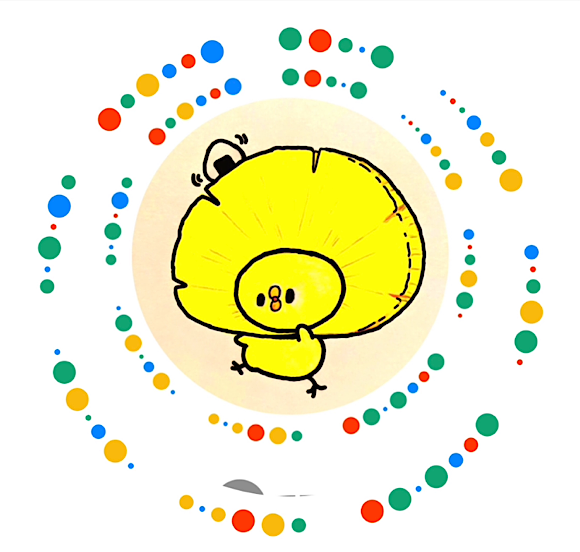
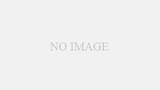
コメント